
新山 海雲 NIYAMA Kaiun
広島県生まれ。
大学卒業後、単身ハワイで起業(飲食)1年間 経営とマネジメントを経験。日本に帰国後、マーケティング/コンサルティング/企画・戦略立案/セールス(新規法人)/PM等の業務を経験。 コミュニケーション能力が評価され5つの部署で業務遂行を任され、結果として社内表彰でCMO賞を受賞。1年で退職。
退職後独立。事業の柱は3つ。コンサルティング事業/マーケティング代行事業(BPO)/新規事業開発、某上場企業の海外支社でのマーケティング部署の立ち上げ(インドネシア)、モンゴルでコスメ系EC 構築、日本最大級の民泊事業会社でのマーケティング部署の立ち上げなど。実務面と経営面の両軸で支援事業を行っている。
新山海雲の強み
1.コミュニケーション能力
傾聴する姿勢を大事にし、会話の中から相手の意見・意図・要望を正確にくみ取ることが得意です。
クライアント自身が問題点を自覚できていない、あるいは何となくつかめているがうまく言語化できていない、ということも
珍しいケースではありません。そのような場合に、クライアントを取り巻く事実やどうなりたいのかというゴールを整理して
まとめ、課題解決に向けて建設的な議論することができます。
2.視点の切り替え/協調性
マーケティングと共に経営課題の抽出から改善も同時に行う施策を考えることができます。自身が起業と廃業を経験していること。
企業内部の組織づくりと、マーケティング実務経験を有していることから、企業へ『資する』と判断した事象や改善案があれば、問題提起し、周りを巻き込んで共に推進していきます。
3.行動力
型に囚われない問題解決力。”ウェブ”マーケティング担当としてアサインされた場合でも、”ウェブ”だけに囚われず、イベントやDMの施策、プロダクトの改善案など、担当領域が違う業務も横断的に行うことができます。
上記のような、強み・経験を生かし、今後も新しい業務に挑戦して参りたいと考えています。
海外事業で得た教訓
私は国内外問わずいくつもの事業展開に関わっていますが、もちろん成功ばかりではありません。失敗から学ぶことも多くあります。
ここでは、実践したからこそ得られた教訓をご紹介していきます。
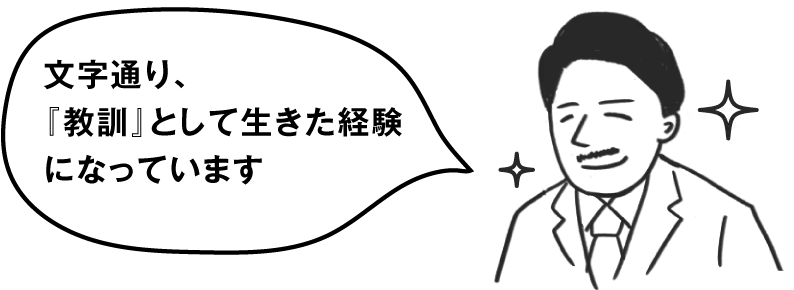
ハワイでうどん屋

私のファーストキャリアの舞台は「ハワイでうどん屋」。
周りの友人たちが大学院への進学や企業に就職していく中、私は違う道を選びました。
ハワイでのうどん屋経営は、現地のマネジメント会社やイベント会社との企画などもあり、最初は順風満帆。
ですが順調に見えた事業にも波が襲ってきました。ハワイの高いコスト、特に家賃・人件費が大きな壁になったんです。
また、目新しさに飽きが来た後は、集客困難で利益が思うように出ない。
試行錯誤するも、2016年10月、泣く泣く帰国。(ちなみに当時ハワイで開業した飲食店(外国から参入した)は、1年で7割が閉店するという話はよく耳にしました。)
この経験から学んだことは本当に多かったです。
新しい市場で商品を作り上げることの難しさ、なによりも「集客」の重要性は痛感しました。
どんなにすばらいい商品も買ってくれるお客様がいなければ成立しません。
でもそれ以上に、お客さんの「おいしい!」という言葉の価値。
そして何より、夢を追いかけることの素晴らしさと、現実をしっかり見つめることの大切さ。
これらの学びは、その後の私のビジネス人生の大切な基盤になっています。
- 新しい市場で商品をつくるなら、集客の施策も持っておくべき
- どんなに素晴らしい商品であってもお客様がいないと成立しない
- 夢を追いかけることの素晴らしさと現実を見つめることの大切さ、そのバランス
セルビアでのオフショア開発

ハワイでの経験の後、しばらく日本でコンサルティング会社に勤めていたんですが、またしても起業への情熱が湧いてきました。
今度は東ヨーロッパのセルビアに飛び立ったんです。
「なぜセルビア?」とよく聞かれました。実は私自身、セルビアについてあまり詳しくなかったんです。
まず大前提に親日国であること。また、3つの魅力的な特徴を聞いていました。
「プログラミング教育が充実している」「英語が堪能な人が多い」「人件費が比較的安い」。
この3つを聞き、現地での創業を考えました。
いわゆる受託業であれば”オフショア開発”、当時流行していたセブ島留学のような教育事業の可能性を感じました。
しかし最大の壁は3つありました。まず、タイムゾーンの違い。
日本の顧客、セルビアのチーム、そして私の間での時差調整は本当に大変でした。
次に、セルビアの複雑な労働法制度。 特に休暇制度は想像以上に手強かったです。
そして最後に、仕事の進め方の文化の違い。日本の「暗黙の了解」が通じない環境での仕事は、新しい発見の連続でした。
結果的にセルビアでの事業立ち上げは、事業継続が難しいと判断せざるを得ませんでした。
でも、チームメンバーたちは最後まで温かく送り出してくれました。

いまでも力を貸してくださった方達とは定期的に交流があります。
この経験から学んだのは、技術だけでなく、文化やコミュニケーションの重要性です。
違う文化の中でビジネスを展開することの難しさと面白さ、そして何より、国際的なチームをまとめることの奥深さを実感しました。使い古されている表現ですが、私がコミュニケーションに重きを置く理由はこの時からだったように思います。
- 海外でのビジネスでは、言葉と文化の壁攻略の難しさを理解しておく
- 文化・コミュニケーションの慣習の違いのある国際的なチームをまとめることの難しさ
- コミュニケーションの重要性
インドネシアでの不動産事業

セルビアでの経験の後、次に選んだのはインドネシアでした。
日本にいるクライアントからのご縁で大きな挑戦の機会を預かりました。
ここでもやはり、最初の壁は言語です。
私が知っているインドネシア語は「Selamat pagi(おはようございます)」だけ。特に不動産業界の専門用語は本当に難しかったです。
毎晩、不動産用語集と格闘しました。「Rumah(家)」「Tanah(土地)」「Sertifikat(権利証)」。
さらには「Hak Milik(所有権)」「Hak Guna Bangunan(建築権)」など、新しい専門用語との出会いの日々。
現地の企業さまの要望がまず、インドネシアの法務に問題ないのか確認をしつつ、開発している物件のプロモーションと収支計画を立て始めました。
現地のクラウアントの主軸事業は、バリ島でのヴィラ開発と、ロンボク島での都市開発事業でした。
しかし、ここでも予想外の課題に直面します。外国人の土地所有制限や複雑な不動産法制度など、理解すべきことが山積みでした。

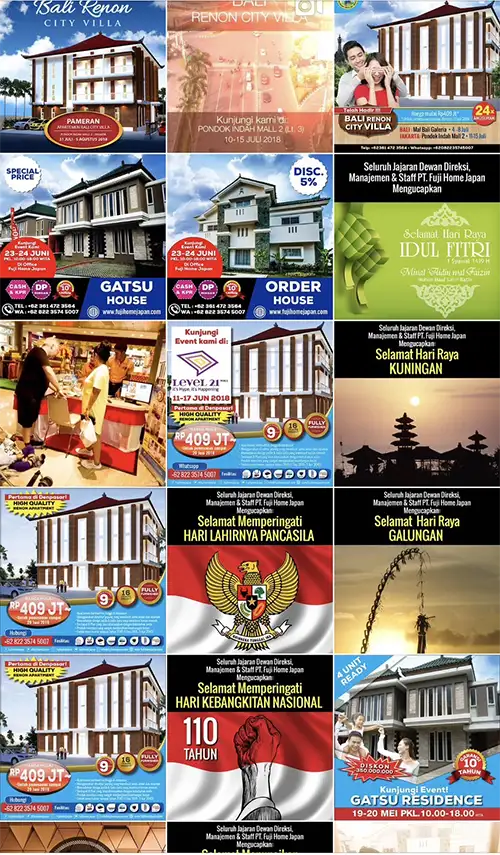
実際に出したバナー広告
またインターネットの利用習慣が日本とは異なり、SNSの使い方も独特で、よくある”マーケティング”として日本で学んだことをそのまま活かすだけでは、なかなか厳しいものがありました。
そんな中2019年末、世界を変えることになる出来事が起きました。COVID-19のパンデミックです。これがきっかけとなりプロジェクトは解散し、私は日本へ帰国しました。
海外でのビジネスを振り返って
ハワイのうどん、セルビアのIT、そしてインドネシアの不動産。一見バラバラな経験に見えますが、実はそこには共通点がありました。
- どの事業でも「時間」(長い目で物事を捉えること)
- 「財務」(考える/試行錯誤できるだけの体力)があること
その前提の上に、いわゆる”マーケティング”といった「市場を理解すること」「文化の違いを受け入れること」「変化に適応すること」は、打ち手の要素であったということ。
業界も分野も違う挑戦でしたが、資本主義の上で生きる私たちが、一定のルールの中で、”経営”をするということの重要な視点だと気づきました。
これらは私が携わったビジネスのほんの一部に過ぎませんが、これらの経験が、私のキャリアを大きく変えることになったのは間違いありません。
今では様々な業界の経営に携わっています。
食品、IT、不動産と、異なる分野での経験が、独自の視点を持つプロフェッショナルとしての強みになっていると感じています。
失敗したように見える経験も、実は最高の”学びの機会”だったと今では感じています。
もし、打開策がほしい、新しい視点がほしいとお考えでしたら、ぜひ私にお声がけください。
国内外問わず様々なビジネスに、濃密に関わってきた私だからこそお届けできる言葉があると自負しています。